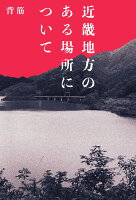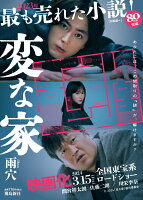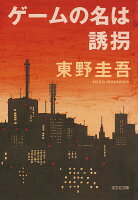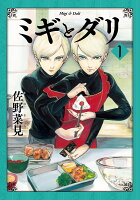こんばんは、紫栞です。
今回は、映画『ある閉ざされた雪の山荘で』を観たので、感想を少し。
こちらは、1992年に刊行された東野圭吾さんの長編ミステリ小説を原作とした映画。
去年原作を読み、この度AmazonPrimeの独占見放題対象になったと知って、早速観てみました。
この映画が劇場公開されたのは2024年1月。そして、今は2024年4月。『スイート・マイホーム』の時も思いましたが、配信されるのメチャ早ですね。
謎演出
ストーリーは概ね原作通り。※原作について、詳しくはこちら↓
キャラクター設定や事件内容の細部、オチのつけ方などに違いがあります。
この物語、有名舞台演出家から手紙で山荘に来るように指示された役者たちが「ここは雪で閉ざされた山荘だという“つもりで”、これから起こる出来事に対応していけ」という、一風変わった設定での物語で、この設定だからこそのミステリが展開されていく訳ですが、この大前提の設定が、映画ではちょっと伝わりにくいのではないかと気になりました。大事なとこなので、もっと分かりやすく劇中で説明する必要があったのではないかと。
案の定、原作未読の方レビューで「何で実際は雪降ってないのにこのタイトルなの?」というご意見があって、やっぱりなぁと。
映像ものであまりにも説明を台詞で喋らせてしまうと無粋になることもありますが、この設定は視覚的に伝えるのは難しいし、ややこしいので、オーディション内容については確りした言葉での説明が必要だったと思います。
前提である設定を理解していないと「この人たち何してるの?」状態で、ストーリー展開にも納得出来なくなってしまいますからね。
東郷先生からのメッセージ、壁に字が映し出されるのですけども、何故あんな風にしたのか疑問。緊張感のない字体だし、声が声優の大塚明夫さんで良い声過ぎるため、現実感が乏しくってチープさに拍車がかかっているなぁと。普通に手紙で良かったのでは?
実際は閉じ込められている訳でも何でも無いのだけれども、電話を使用したり、外部の人間と接触した時点で試験は中止。オーディション合格も即刻取り消すという指示のため、不審な点があっても皆館から逃げ出せない・・・と、いう設定なのですが、ビデオカメラで隠し撮りした映像に犯行シーン的なものが映っているのまで見てしまっては、流石に館から逃げ出すのでは?この状況で館に皆が残るのは心情的に無理がある。
92年の小説作品を現在設定に直してのものなので、現在感を出したかったのかもしれませんが(東郷先生のメッセージも)、隠し撮りの付け足しは余計だったと思いますね。
原作小説の方ですと、館の見取り図が本格推理小説らしく本の最初に表示されていまして、真相を見破るヒントになっています。
この映画でも見取り図を映すシーンが沢山ありまして、原作を読んだ私は「ああ、見取り図はヒントだもんね・・・」って、最初思ったのですが・・・・・・いや、よくよく見ると原作と見取り図まるで違うんだが!?
これじゃヒントになんてならないし、推理もまるで変わってくる。いったい何のためにこんなに何度も何度も映していたのか・・・謎すぎる演出です。
※以下、ガッツリとネタバレ含む感想となりますので注意
推理してない
私がこの映画で最も問題だと思うところは、推理ものなのに推理をしていないところです。
この物語、殺人劇の舞台稽古→舞台稽古に見せかけて本当に殺人が起こっている?→と、見せかけてやっぱりお芝居
という、三重構造が肝になっているミステリなのですが、推理の過程がほぼ描かれないのと、上記したように館の間取りを原作から変えてしまっているため、主人公の久我(重岡大毅)が真相に行着くための手掛かりが圧倒的に足りない。
推理として具体的に語られるのは電子ピアノのヘッドホンについてぐらいで、この手掛かりからでは百歩譲って三重構造を見破ることが出来たとしても、雅美(森川葵)が潜んでいる場所、そもそも館に潜んでいるのだと解るとは思えない。
これじゃあほとんど勘で当てているようなもの。推理ものとしてのロジックがまるで無視されています。
やはり茶番
原作は、憎い相手を雅美に言われた通りに目の前で殺してみせることで、自分がやろうとしている事の恐ろしさに気づいてくれればいいという本多(間宮祥太郎)の想いがあって七面倒くさい三重構造芝居をしたというものでした。
最後には雅美が、途中からこれは本多が仕掛けた芝居だろうと気がついていたと告白。憎んでいた三人に「芝居をやめるつもりだ」と謝罪され、「あなたたち、芝居はやめないで」「芝居はいいものよ。素晴らしいわ。改めて、そう思ったもの・・・・・・」と言って、それを聞いたメンバー全員で泣いて終わる。
ちょっと茶番感溢れる大団円ですが、雅美が考えを改めてくれて、芝居の良さを思い出させることも出来たし、七面倒くさい本多の三重構造芝居も意義があったといえるオチになっています。
しかし映画ですと、雅美は久我に言われるまで本多たちの芝居には気がついておらず、真相を聞いて一旦は怒るものの、その後三人に謝罪されて「一緒に芝居やろう!」と言われてあっさりと受け入れて芝居して終わっています。
原作とはまた違う茶番感のハッピーエンドですが、これですと本多がやったことほぼ意味なかったというか、「最初から三人に誠心誠意謝罪させればそれで良かったんでは・・・?」ってなってしまって、ハッピーエンドですが釈然としない。
各人物のキャラクター性も弱くって、心情などついていけないところがチラホラリ。特に、雅美が三人を殺そうと思った経緯がほぼ逆恨みに近いものに変更されていたのは残念でした。
本多が雅美を好きとか、雅美が雨宮(戸塚純貴)を好きとか、恋愛事情も分かりにくかったですね。
と、いうか、正直、全部分かりにくかったんですけど。原作読んでいない人、この映画観てちゃんと理解出来るのだろうか?疑問ばっかり残るんじゃ。
また、この映画ではガン無視されていますが、原作は小説ならではの叙述トリックが仕掛けられたものになっていて、実はそこがメインです。そう、この映画は原作である推理小説のメイントリックが省かれているという、ある意味とんでもない作品なのですよ・・・。
そんな訳で、個人的には納得のいかない映像化でしたが、高評価をしている人も結構いて、楽しみ方は人それぞれだと改めて思い知らされました。とりあえず、私はミステリ映画としては評価出来ないんですけど・・・。
映画観た方は原作も是非。
ではではまた~